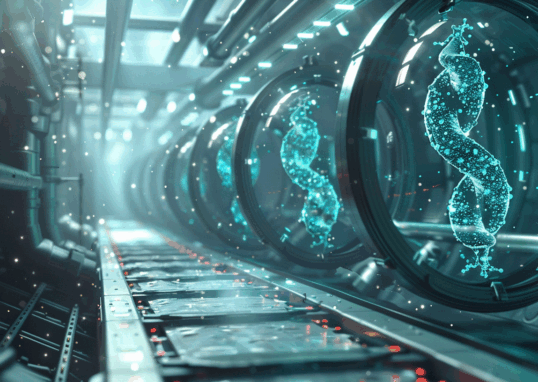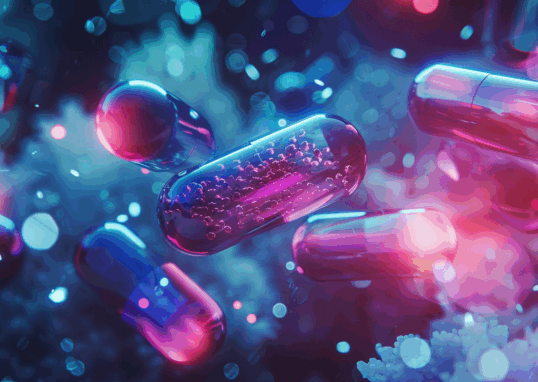はじめに:PMSの終焉は、進化なのか?
日本の製薬業界にとって「製造販売後調査(PMS)」は、長らく安全性と有効性を担保する重要な制度でした。しかし、近年、厚生労働省とPMDA(医薬品医療機器総合機構)は、急速に進化するデジタルヘルス技術や医療ビッグデータの潮流を受け、RWD(Real World Data:リアルワールドデータ)を薬事戦略に取り込む動きを強めています。
この記事では、PMSの役割と限界、そしてRWDの可能性と注意点を、日本市場の現状とグローバルトレンドを交えてわかりやすく解説します。
PMS制度の限界と課題
PMSは医薬品承認後の安全性・有効性を確認する義務調査であり、特に日本では企業が責任を持って実施する義務が課されています。しかし、以下のような課題が顕在化しています。
- 時間とコストの膨大さ
実施には平均で3〜5年、数億円のコストがかかる場合もあり、中小企業にとっては大きな負担となります。 - 症例収集の困難
調査対象の症例が限定的で、データの偏りや信頼性への懸念がつきまといます。 - 臨床現場との連携不足
医師の協力が得にくく、診療実態と乖離したデータとなることもあります。
こうした背景のもと、より効率的で現実的な手法として、RWD活用が脚光を浴びているのです。
妊娠〜出産〜子育て中の「ママ」のための保険無料相談サービス【ベビープラネット】RWDとは何か?その定義と日本における主なデータソース
RWD(リアルワールドデータ)とは、日常の臨床現場で収集される医療データのことを指します。日本では以下のようなデータソースが存在します。
- DPCデータ(診断群分類):入院医療の標準化データ
- NDB(ナショナルデータベース):レセプトと特定健診情報を網羅
- MID-NET®:PMDAが運用する医療機関連携型のEHRデータ基盤
- 患者レジストリ・PRO(患者報告アウトカム):特定疾患や副作用の長期追跡データ
これらのデータを利活用することで、PMSに匹敵する、あるいはそれ以上の信頼性を持つ実世界のエビデンス(RWE:Real World Evidence)を構築できるのではないか、と期待されています。
規制当局のスタンスと具体的な活用事例
TOEIC対策は、最小の努力で最大の結果を『SHADOM ENGLiSH』PMDAは近年、RWDを活用した薬事戦略を容認する方向で明確なメッセージを打ち出しています。たとえば、再審査申請におけるRWD活用、または医薬品のリスク管理計画(RMP)における副作用モニタリングとしての応用が進んでいます(PMDA, 2021)。
欧州や米国でも同様の動きが活発であり、米国FDAは「21st Century Cures Act(2016)」を契機に、RWD/RWEを用いたラベリング変更や適応拡大を正式に認め始めています(FDA, 2018)。
RWD活用のメリット
以下の表に、RWDを活用することのメリットを記載します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 多様な患者層の反映 | 高齢者・多疾患併存患者など、RCTでは対象外の群を含む |
| 長期・大規模データ | 数年単位・数十万件のデータをリアルタイムで取得可能 |
| コストと時間の削減 | PMSと比べてはるかに短期間・低コストで分析が可能 |
| 臨床実態との整合性 | 実際の医療現場の診療パターンや薬剤使用傾向を反映 |
しかし、当然ながらRWDも万能ではない!注意すべき課題とは
RWD活用には明確な利点がある一方で、次のような課題も無視できません。
- データの質と不完全性:特にEHRデータでは、入力のばらつきや欠損値が多く、解析上のバイアス要因となる
- 標準化の遅れ:施設ごとのコードや分類体系の違いにより、比較解析が困難
- 倫理・個人情報保護:GDPRやAPPIなどの規制を遵守した匿名化・二次利用のルール整備が不可欠
- 因果推論の限界:RWDはあくまで観察研究であり、RCTと異なり介入の効果を直接証明することは相当難しい
したがって、RWDを活用するには統計学的スキル、臨床的知見、倫理的配慮を統合した専門チームが必要不可欠です。
今後の薬事戦略における実務提案
ここからが、以上のメリット・デメリットを踏まえた上での実務提案です。
- PMS設計段階からRWD連携を前提としたハイブリッド戦略を構築
- DPCやNDBなどの信頼性の高い公共データを利用した解析手法を社内で内製化
- RWD解析に精通したCROやベンダーとの連携強化
- 国際規制動向(FDA、EMA、PMDA)を踏まえたRWE生成フレームワークの構築
- 医療機関・患者との信頼関係構築とインフォームド・コンセントの最適化
結論:RWDはPMSを代替する「手段」ではなく、「戦略」と考えるべき
PMS制度の見直しとともに、RWDは単なる代替手段ではなく、薬事の未来を再設計する戦略的資産になりつつあります。データの「量」から「質」、そして「意味」へと転換を図る時代において、製薬企業には真のEvidence Generatorとしての覚悟と準備が求められます。
PMSを卒業し、RWDを武器に世界市場で戦える薬事戦略へ──。それが今、問われていると言えます。
つまり、今後の製薬企業にとって重要なのは、単にRWDを収集・解析する技術力だけではなく、いかにそれを規制当局・医療機関・患者と信頼関係の中で共有し、社会的合意と臨床的インパクトを伴った「価値ある証拠」に昇華できるかという戦略眼です。RWDを通じて、患者中心の医療を実現し、医薬品開発と市販後のライフサイクル全体における最適解を提案できる企業こそが、これからのグローバル薬事の舞台で主導権を握ることになるでしょう。
参考文献
- FDA (2018). Framework for FDA’s Real-World Evidence Program. [online] Available at: https://www.fda.gov/media/120060/download
- PMDA (2021). Real World Dataの利活用に関する報告書. [online] Available at: https://www.pmda.go.jp/
- Makady, A., et al. (2017). What Is Real-World Data? A Review of Definitions Based on Literature and Stakeholder Interviews. Value in Health, 20(7), 858–865. https://doi.org/10.1016/j.jval.2017.03.008
- Schneeweiss, S. (2019). Real-World Evidence of Treatment Effects: The Useful and the Misleading. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 106(1), 43–44. https://doi.org/10.1002/cpt.1443